|
台湾有事でリスクに晒されるシーレーン、食糧を輸入に依存する日本は大丈夫か

(出典:2022年3月23日 JB press)
もし中国による台湾や尖閣諸島侵攻が始まり、南シナ海や東シナ海のシーレーンが閉鎖されてしまうと、日本向けの原油や天然ガス、そして輸入農産物の大半が入ってこなくなる可能性があります。
石油タンカーやコンテナ船が入港できなくなると、日本でも食糧危機が起こるのは確実です。最終的に、政府や企業が協力し合って対応することになりますが、その間、食料が不足する状態が一定期間続くことになります。
上記の記事を書かれた、農水省出身でキヤノングローバル戦略研究所研究主幹の山下一仁氏は、シーレーンの閉鎖によって食糧危機に近い状態を日本は過去に何度も経験している、と説明しています。
まず、77年前の終戦直後に起きた食料難は不作の年で、当時、農林省が管轄する倉庫には3日分の米しかなかったということです。戦前は、朝鮮や台湾という植民地から米を輸入していましたが、戦後は戦争で稲を植えることさえできなかったようです。
大穀倉地帯であるウクライナでも、戦争の影響で小麦などの作付けが送れていると報道されています。つまり、戦争によって収穫量は激減し、輸入も途絶えるということです。1946年当時の日本の人口は約7000万人でしたが、そのうちの1000万人が餓死すると言われていました。
声 語りつぐ戦争:食べ物

(出典:朝日新聞)
米や麦、イモ類などの食料は政府の管理下に置かれ、国民は配給通帳と引き換えに指定された小売業者から購入する配給制度が導入されていました。50代前後の世代は、両親が子どもの時に「ふすま」を食べたことを聞かされているはずです。
ふすまは、小麦を精製するときに出る胚芽と表皮の部分で、とても美味しいとは言い難いものです。小麦粉(全粒粉)にふすまの入ったすいとんを代用醤油をかけ、麦を入れた玄米ご飯で食べたとされています。
話を現代に戻しますが、戦争でシーレーンが閉鎖された場合、当然、小麦や肉類は入ってこなくなります。輸入穀物(肥料)に依存している畜産家はほぼ壊滅し、最低限のカロリーを摂取できる食生活、つまり米とイモ類だけの終戦後のような食生活に戻るしかなくなります。
農水省ホームページ:その1:食料自給率って何?日本はどのくらい?
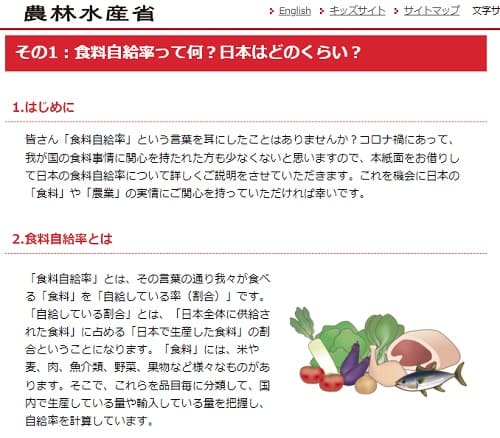
(出典:農林水産省)
当時、1日1人あたりの米の配給は2合3勺(345グラム)で、年間では125キロと計算できます。ちなみに、現在の1日1人あたりの米の消費量は50キロしかありません。現代人の多くは、1日2食しか食べなかったり、そばやうどん、パン、パスタなどを食べています。
日本人が、実際に食べている穀物量は年間159キロです。ところが、肉類や牛乳、卵などのタンパク質の原料になる肥料を輸入できなくなると、副食からカロリーを摂取することができなくなるため、国内で生産できる米やイモ類のだけで不足するカロリーを補わなければならなくなります。
だからこそ、玄米の備蓄や家庭菜園などで野菜を栽培する必要があるわけです。しかし、都市生活者の住宅は狭くて備蓄スペースがなく、家庭菜園ができるほどの庭もないのが現状です。
日本の食料安全保障の真相 「台湾有事で日本人の半数は餓死」?
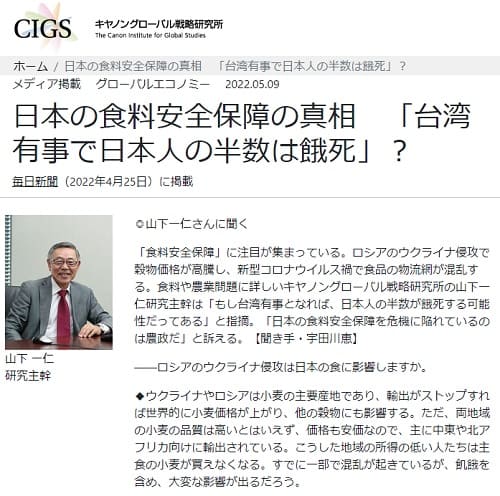
(出典:2022年5月9日 CIGS キャノングローバル戦略研究所)
山下氏の試算によると、全人口の約1億2500万人に345グラムの米を配給するには、約1500万トンが必要です。そして、2022年度の主食用米の供給量は約700万トンしかありません。私たちは、その倍の米を今から確保する必要があります。
日本政府は、これまで米の減反政策を進めてきましたが、家畜用の米や政府・JAなどの備蓄米を含めると+100万トン=800万トンしかありません。残りの700万トンを捻出するための解決方法は、休耕田を復活させてすぐにでも農地に切り替えることです。
|