|
1からわかる!南海トラフ巨大地震(2)私たちの生活はどうなるの?
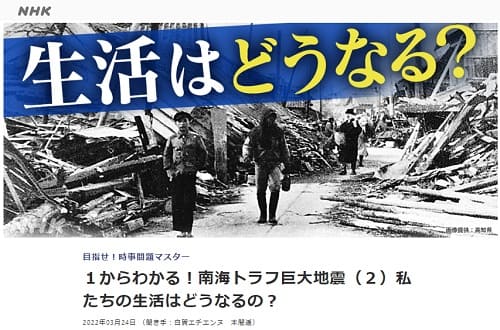
(出典:2022年3月24日 NHK)
今後、コロナ騒ぎから始まったウクライナ戦争までの人災によって、意図的に食糧危機を起こされる準備が整いつつあります。
日本では、大型台風や異常気象など未曾有の自然災害が頻発しています。しかし、多くの災害は日本の国土の豊かさの裏返しでもあります。毎年、土地に豊かな水を供給して恩恵をもたらしてくれていた河川が氾濫し、洪水などの被害が起きています。
実際に、世界の火山の約7%が日本に存在しているため、マグニチュード6以上の地震の約20%が起こっています。保険料の支払額のトップ3が、阪神淡路大震災の783億円、熊本地震の3750億円、そして東日本大震災の1兆2750億円と日本が占めています。
日本の法令上の自然災害は、「暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、噴火その他の異常な自然現象により生ずる被害」と定義されています。被害を最小限にするために、私たち日本人は備蓄や防災の知識を身につけ、日常から備える必要があります。
基本的に、首都圏などの大都市から郊外に移住するか、いつでも移住できるセカンドハウスを借りておき、農地も借りて野菜や果物を育てることです。週1回程度の水やりや雑草抜きなどの手間がかかりますが、情報収集のためにも郊外に出ておくことが求められています。
私自身、米軍で学んだことは同じレベルの生活ができる場所を、移動距離を考えて複数持つことでした。暴風や地震などで住宅が破損した際、着の身着のまま入居できる部屋を持つと生存率が格段に上がることがわかっています。
聴く防災訓練

(出典:Tokyofm)
世界最大の危機管理国家であるアメリカは、最高レベルの科学技術を持つ国防総省の研究者を米軍所属としてあらゆる分野で動員しており、運用体制を構築しています。また、大学や政府系シンクタンクでも技術やノウハウは生かされています。
米軍では、必ず同じ機器は複数保有して運用しています。戦艦や戦闘機、さらに大統領専用機(エアフォース1)や専用車(ビースト)に至るまで電子機器が壊れても、同じ機器ですぐに代用できるシステムが組み込まれています。
つまり、冷蔵庫を2台、ストーブを2台持つことは基本中の基本であり、今住んでいる自宅とセカンドハウスにそれぞれ設置しておく必要があります。2台目は中古品でも構わないので、全く同じ商品にすることです。
2階建ての一戸建て住宅の場合、地震や洪水によって1階部分が倒壊して2階に避難するケースが東日本大震災や熊本地震では多かったようです。だから、備蓄している玄米や水は2階にも置いておく必要があります。
何が起きても2階に物資を取りに行ける経路や方法も考えておき、隣の家の倒壊や暴風雨、火災に巻き込まれないように頑丈な構造を持つ収納スペースにも分散し、さらに車にも入れて置くとリスクが緩和されて生存率が高まります。
「まずは自分で備えを」ライフライン寸断時にあったら便利な物震災経験の防災士が勧めるサバイバルグッズ

(出典:2022年3月12日 uhb北海道文化放送)
最近、地下に核シェルターを設置する世帯が増えていますが、そこに全て備蓄しておくことも可能です。しかし、建物に潰されて外に出られなくなることもあり、安全性を確保しながら経路や方法をイメージしておきます。
もし長期的に停電が続いた場合、ソーラーパネルによるバッテリーシステムが有効ですが、冬の北海道では雪が積もって全く発電しないことがあります。車のバッテリーを利用したインバーターを用意しておけば、災害時にも洗濯機などを動かせるようになります。
ただし、長時間の利用にはガソリン代がかかるので、乾電池式の灯油ストーブを2台以上用意しておきます。当然、灯油の備蓄が必要ですが、安全に保管できる場所を選んで原油価格高騰や円安に対応しておきます。
ウクライナ侵攻で「世界食料危機」の懸念が高まるも、日本の食料自給率向上は「アメリカが絶対許さない」理由
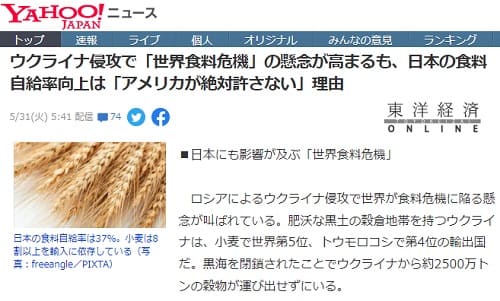
(出典:2022年5月31日 Yahooニュース)
そして、断水が起きた場合、一人当たりの飲み水は2リットル程度ですが、トイレで流す水は10リットル以上必要です。近くに水が湧き出ている場所を特定し、20リットルのポリタンクでいつでも汲めるようにしていきます。
山から流れてくる水は、エキノコックスなど病原菌が混入しているケースもあり、煮沸することが基本です。冬はストーブの上にやかんを置いて沸騰させますが、夏は料理用のカセットコンロをベランダで使用する必要があります。
寒い冬には湯船に浸かって温まりたいですが、停電してなお且つ水が不足している状態では火にかけて水を温めてシャワーにするしかありません。給水車など自治体が用意したサービスだけに頼るのではなく、孤立した状態でも工夫する体制に整えておきます。
そして、長期的に食料の自給自足が可能な体制を整えておくことが重要です。家庭菜園や農地の確保、種まきから水やり、雑草抜き、そして収穫など普段から運用に慣れておきます。
以上、人間が生きるために最低限必要な電気や水、食料、そして居住環境を確立していくことで、自分自身と家族を守ることができるということです。次回は、避難所での被災生活についてコラム化していきます。
|